INTERNAL MEDICINE -01
一般内科

体調不良の際に初めに受診することが多い「一般内科」は、最適な医療をご案内するための最初の窓口となります。当院では発熱、風邪、インフルエンザ、コロナ感染症を除く、頭痛、腹痛、下痢、胃痛、めまいなどの急性疾患や、生活習慣病などの慢性疾患に至るまで、内科の様々な診療を実施しています。ちょっとしたことでも遠慮なくご相談ください。どの科を受診すれば良いか分からないという方は、各患者様の病状や病気を専門とする医療機関や診療科にお繋ぎしますので、一度ご相談ください。当院では発熱外来・感冒外来を停止しておりますのでご理解の程、よろしくお願いします。
生活習慣病

生活習慣病は、高血圧、糖尿病、痛風(高尿酸血症)、脂質異常症などが知られています。食べ過ぎなどの食生活の乱れ、運動不足、肥満などの生活習慣の乱れなどが発症に大きく影響すると考えられています。軽症だったとしても、複数の病気を併発すると、脳卒中や心臓疾患などの深刻な病気が起こりやすくなります。なお、発症初期は自覚症状が乏しく、体調不良を感じて受診した時点では既に重篤な状態になっている恐れもありますので、ご自身の生活習慣を改善し、発症を防ぎしょう。当院では、最初に生活習慣の改善から取り組みます。例えば、運動療法や食事療法を行い、必要があれば薬物療法もご案内いたします。当院の栄養士による栄養指導も受けることができます。
高血圧

高血圧は日本人が発症しやすい疾患で、40~74歳の男性の60%程度、女性の40%程度が発症するとされています。高血圧を放っておくと血管に負担がかかり、動脈がダメージを受けます。また、心臓は大きな圧力で血液を送るために、エネルギー量が増加し、疲れを感じやすくなります。つまり、高血圧では心臓や血管の負担が大きくなり、血管がダメージを受けることで硬化し、動脈硬化、狭心症、心不全、心筋梗塞などの心臓血管系の疾患のリスクが高まるほか、脳梗塞、脳出血、腎臓疾患も起こりやすくなります。当院では、最初に減塩、適度な運動、ダイエットなど、生活習慣の見直しを実施します。ご自宅で定期的に血圧を測定して頂き、血圧の状態を見ながら降圧剤をお渡しします。血圧がなかなか下がらない方、若年~壮年期の高血圧の方、診療所見で高血圧を引き起こす別の疾患の恐れがある方などは、二次性高血圧も考慮し、ホルモンなどの検査を実施します。
脂質異常症

脂質異常症は、血中の中性脂肪やコレステロールなどの脂質が過剰になることで発症する疾患です。コレステロールは善玉(HDL)コレステロールと悪玉(LDL)コレステロールに分けられます。善玉コレステロールは、血管や細胞の中の過剰な脂質を回収する働きがあり、悪玉コレステロールを減らします。しかし、中性脂肪や悪玉コレステロールが過剰な状態を放っておくと、脂質が次第に血管内部に蓄積して動脈硬化が進み、脳梗塞や心筋梗塞を引き起こします。高血圧などと同じく自覚症状が乏しいため、早期発見のためにも健康診断などを定期的に受けましょう。中性脂肪や血中コレステロールの値が高い方は、一度当院までご相談ください。
脂質異常症は、他の生活習慣病と同じく、運動療法や食事療法、薬物療法により治療を行います。運動療法では、ウォーキングなどの軽めの有酸素運動を継続することで、中性脂肪が減少し、HDLコレステロールが増加すると言われています。また、食事療法では、高LDLコレステロール血症の方は、動物性脂肪が多い食品の摂取を控え、植物性脂肪を積極的に摂る、きのこ類や野菜などの食物繊維が多い食品を摂る、コレステロールが多い食品の摂取を控えることをお勧めします。また、高中性脂肪血症の方は、飲酒や糖質が多い食品の摂取を避ける、カロリー制限を行うことをお勧めします。薬物療法では、中性脂肪やLDLコレステロールを減らすお薬など、各患者様に合った適切なお薬を使用します。
糖尿病
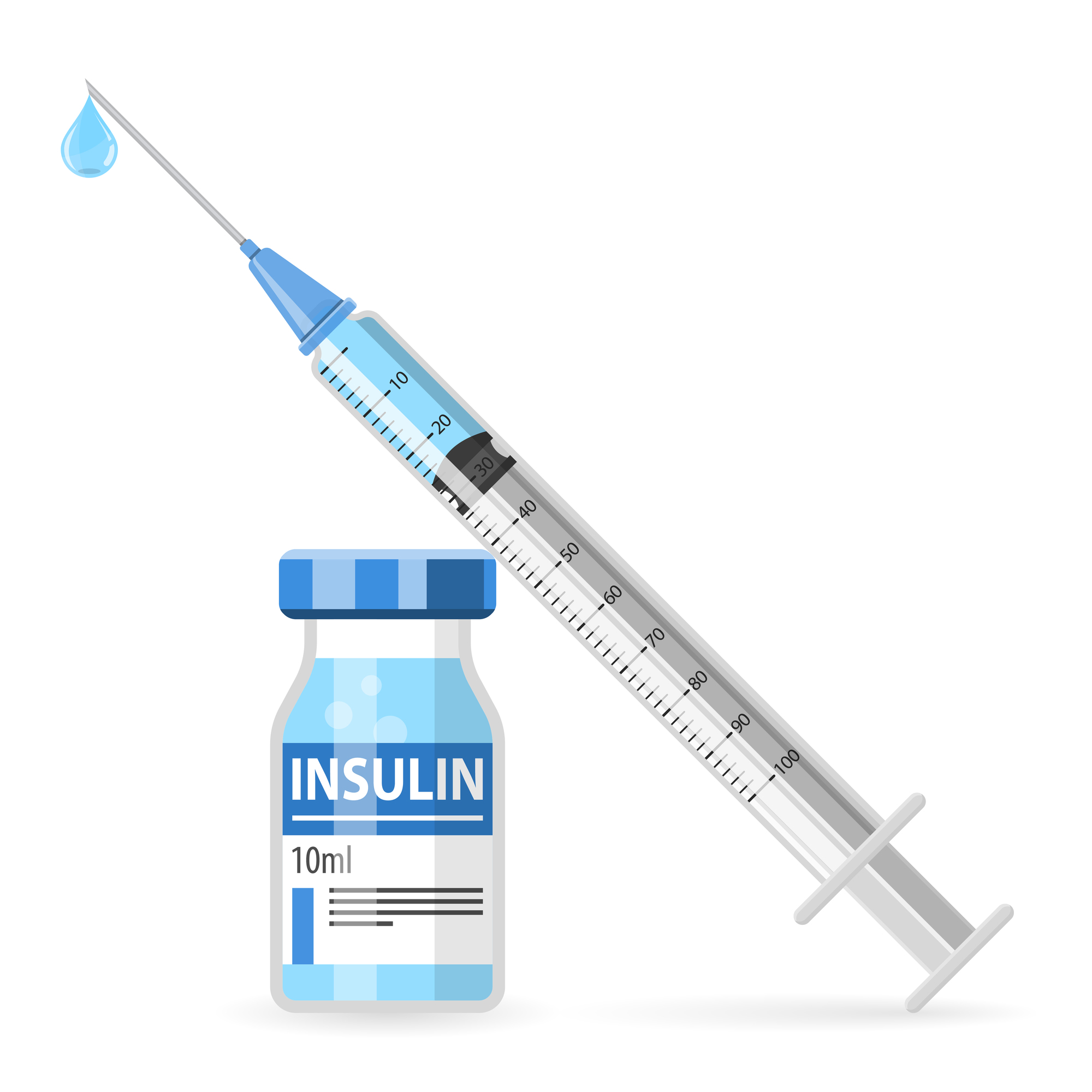
糖尿病は、体内でインスリンの分泌量が不足したり、インスリンの働きが悪くなったりすることで、血液中の糖(血糖値)が高い状態が続く疾患です。日本では約1,000万人の患者さんがいると推定され、予備群を含めると約2,000万人に上ると言われています。
糖尿病は1型(インスリン依存型)と2型(インスリン非依存型)に大きく分けられ、日本人の場合は95%以上が2型糖尿病です。2型糖尿病は、食べ過ぎや運動不足などの生活習慣の乱れ、肥満、遺伝的要因などが複合的に影響して発症します。初期段階では自覚症状がほとんどなく、「のどの渇き」「多飲」「多尿」などの症状が現れる頃には、既に病状がかなり進行していることがあります。
糖尿病の主な症状は以下の通りです
1 多尿(頻尿)
糖尿病では、血糖値が高いために腎臓が余分なブドウ糖を尿中に排出しようとします。その結果、頻尿や多尿の症状が現れることがあります。
2 絶え間ない喉の渇き
高血糖の状態が続くと、体は水分を失って脱水状態に陥ります。そのため、常に喉が渇いていると感じることがあります。
3 飢餓感や増食欲
体が血糖を効果的に利用できないため、エネルギーが不足している状態が続きます。その結果、飢餓感を感じやすくなり、食欲が増加することがあります。
4 体重の急激な増減
糖尿病の初期段階では、体重が急激に減少することがあります。これは、体がブドウ糖を利用できず、脂肪を分解してエネルギーを得るためです。一方、一部の糖尿病患者では、高血糖の治療が行われる前に体重が増加することもあります。
5 疲労感
高血糖の状態が続くと、体内のブドウ糖を効果的に利用できなくなり、エネルギー不足が起こります。このため、疲労感や倦怠感を感じることがあります。
6 傷の治りが遅い
高血糖は、血液の循環を悪化させることがあります。このため、傷や擦り傷の治りが遅くなることがあります。
放置すると、網膜症による視力低下や失明、腎症による腎不全、神経障害によるしびれや痛み、さらには動脈硬化が進行することで心筋梗塞や脳卒中などの重大な合併症を引き起こす恐れがあります。これらの合併症は一度発症すると完全に元に戻ることはないため、早期発見と適切な治療・管理が非常に重要です。
当院では、血糖値やHbA1cの検査を行い、糖尿病の診断と治療を実施しています。治療においては、まず食事療法と運動療法による生活習慣の改善から始めます。具体的には、適切なカロリー制限と栄養バランスの取れた食事指導、日常生活に無理なく取り入れられる運動プログラムの提案を行います。当院の管理栄養士による個別の栄養指導も受けることができます。
生活習慣の改善だけでは血糖コントロールが難しい場合は、経口血糖降下薬やインスリン注射などの薬物療法も組み合わせて治療を進めます。また、定期的な検査により合併症の早期発見にも努めています。
糖尿病は「治る」病気ではありませんが、適切な管理により健康な人と変わらない生活を送ることが可能です。少しでも気になる症状がある方、健康診断で血糖値が高いと指摘された方は、ぜひ当院にご相談ください。
また、初めて糖尿病を指摘された方や急に糖尿病が悪化した方は「すい臓がん」が隠れている可能性がありますので、当院にご相談ください。
発熱外来・感冒外来の停止 (発熱や風邪症状の患者さんの受診について)
現在、当クリニックでは発熱ならびに風邪症状患者さんの診療を停止しております。
発熱患者様は他の医療機関の受診をお願いいたします。
受診後に発熱や風邪症状が発覚した場合は、外のブースで必ずコロナ感染のチェックを受けていただきますのでよろしくお願いします。
当日だけではなく、数日以内に高熱(38℃以上)が出た方は、必ず事前にお電話にてご一報ください。
また、身近な人がコロナ確定またはインフルエンザ確定した方も、必ず事前にお電話にてご一報ください。
定期受診の方はお電話で受診時間を設定しますので、その時間帯に受診をお願いします。
受診時間は、当日の予約診療の状況によって変わりますのでご了承ください。
お知らせ
- 待合時間の負担軽減
- 待合室の混雑緩和
- 感染予防対策
上記の観点から、事前予約優先制にて診療を行っています。
当日の予約状況によっては、新規の患者様でご予約なしの場合は診療をお受けできないこともありますので予めご了承ください
当院の診療時間について
この度、午後の診療時間を以下の通り変更させていただくことになりましたので、お知らせいたします。
皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
変更後の午後診療時間
- 診療時間: 16時〜17時まで
- 最終受付時間: 16時30分
※診察はWeb予約の患者様のみとなります。
※午前の診療時間に変更はございません。
※変更は2024年11月1日より適用されます。
※水曜日は「休診」となっておりますのでご注意ください。電話対応も出来かねますのでご了承ください。












